トップ > 研究開発 > 製剤化研究・容器開発 > 品質をかたちにする技術センターの取り組み
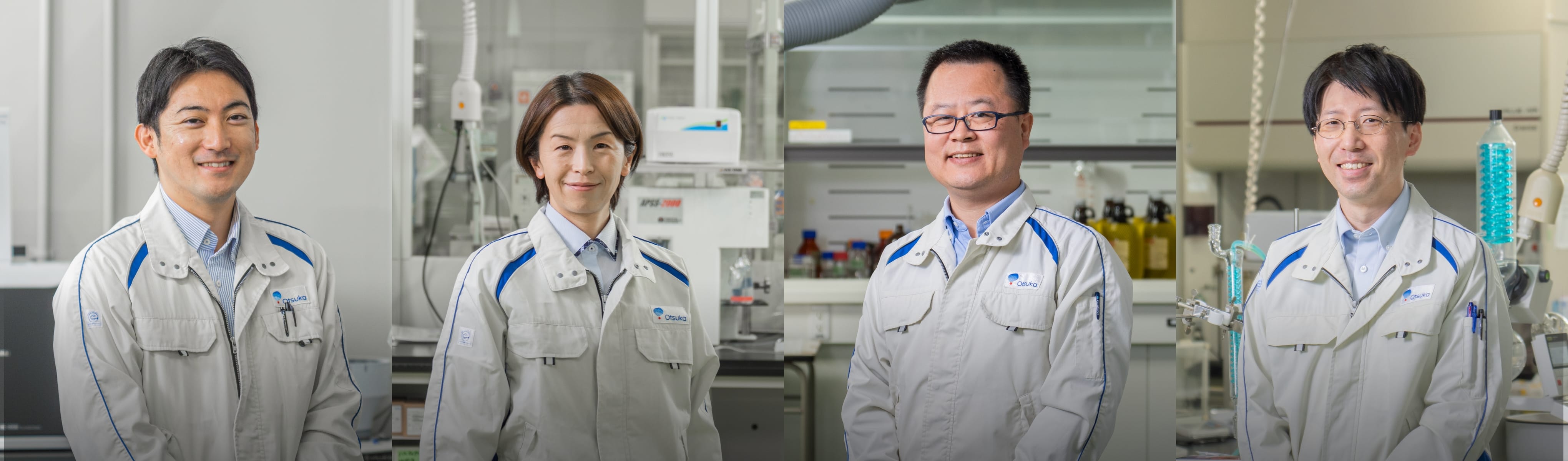
技術センターでは、製剤技術部と生産技術部が同じフロアに集結。風通しの良い環境でコミュニケーションとコラボレーションを密に行い、製品の品質を磨き抜き、国内のみならず世界へ安心をお届けしています。

技術センター 製剤技術部 製剤研究第3グループ リーダー 三本 雪美
大学や大学院ではウイルス学を専攻し、研究の一環としてHPLC(高速液体クロマトグラフィー)という測定機器を用いた分析を数多く行っていました。入社後は輸液の分析評価に携わり、大学時代の経験を生かすこともできて、この仕事は自分に合っていると思いました。
製剤研究グループに異動してからは、外用薬の製剤化研究、海外申請の支援、生産や営業の支援を行っています。業務内容は幅広く、製剤研究では処方検討だけでなく、原料・容器・包装などの選定と評価、委託製造の場合は他社との技術的な折衝も行う必要があります。リーダーの役割は、さまざまなテーマについてグループの各メンバーが検討を進める過程での方向性やスケジュールの確認、相談などマネジメントが主な業務です。
今も、あるテーマで進めている設計開発のユーザビリティエンジニアリングの責任者として、開発品の安全使用に関わる仕様の検討や評価を行なっているところです。仕事は大変ですが、製品への愛着も湧きますし、実際に使用していただいている医療機関の現場の声に触れることもできて、人の生命や健康に寄与しているという実感も得られ、大きなやりがいにつながっています。

技術センター 生産技術部 課長補佐 韓 暁明(かん しょうめい)
中国の大学を経て来日し、大学院で生命科学を専攻しました。入社時に配属された海外技術部では、海外の子会社に対してさまざまな技術的支援を提供し、中国語はもちろんのこと他の国の言語も知っていることが大いに役立ちました。
現在は生産技術部に所属して、医療用医薬品、消費者製品の国内外の製造工場の検討や、材料関連の開発業務を担当しています。当社は、南アジア、東南アジア、アラブ、中国エリアなどの13カ国・エリアに製造工場を有しており、そうした現場で新しい生産ラインの導入や、新工場の建設といった計画を推進するにあたっては、大塚製薬工場の品質ポリシーを遵守する必要があります。
ところが往々にして、それらの国の人々は品質に対する認識が日本とは異なります。そのため、文化的な土壌の違いを受け入れつつ、根気よくコミュニケーションを続け、私たちの考え方を理解してもらい、根付かせていく地道な努力が不可欠でした。
今は、国内4工場の重要な技術課題への対応や部内環境の改善、情報共有の円滑化の推進などの業務に軸足を移していますが、私にとってコミュニケーションの大切さは重要なテーマであり続けています。

技術センター 製剤技術部 再生医療担当 リーダー 椿山 諒平
入社時に配属された製剤技術部で、消毒用の製剤開発から申請までの業務を受け持ち、その後、当社の新しい事業として、いわゆる再生医療の領域での挑戦がスタート。新たなチームの一員として加わることになりました。
私の場合、大学は工学部なのに、大学院では分子生物学を専攻し、入社後はまったく畑違いの製剤開発ということで、いつも何か新しいことにチャレンジしてきました。さらに現在は、これまでとは次元の異なるまさに未知の領域で仕事をしています。
その一例が、糖尿病治療用のバイオ人工膵島です。ブタの膵島細胞をカプセルに閉じ込めたカプセル化ブタ膵島細胞で、「カプセル」と「再生医療」という異なる機能が融合した非常にユニークな製品です。糖尿病の治療薬として世界から注目されており、1日も早くお届けできるよう開発を進めてきました。
こうした製品の設計、製造検討、申請対応などは、チームの誰もが経験したことのないものばかりでしたから毎日が手探りの状態で、もちろん失敗もありました。でも、だからこそ、業務を通じた学びや刺激が多く、私にとってはすべてが新鮮で、とてもやりがいを感じています。

技術センター 生産技術部 新技術開発担当 リーダー 藤原 和司
高等専門学校では生物応用化学のコースに進み、柿の熟成方法など農学寄りの研究をしていました。入社して10年間は、北海道の釧路工場にある生産技術部釧路分室に勤務し、高カロリー輸液用のエルネオパ輸液やビタミン、微量元素の処方を改良したエルネオパNF輸液の製剤立ち上げなどの業務に携わってきました。
その後、現在の部署に異動し、ここでは環境に配慮した輸液用ボトル容器や包材の設計開発と、工業化に向けた製造技術の検討を行っています。具体的には、容器・包材として使用する樹脂の処方開発と、CAE(コンピュータ工学支援システム)による強度・機能性のシミュレーション解析を活用した形状設計および評価です。
また、工業化に向けては、量産時に安定生産が可能な製造条件の検討、滅菌方式・条件などの検討を実施します。それだけでなく、これがもっとも重要とも考えているのですが、開発品を医療機関の方が手に取り、どのような印象をお持ちになったか、実際に触れたときの感触や操作したときの感覚などをヒアリングします。このように直接、医療従事者の声を聞き取り製品作りに生かすというのは、大塚製薬工場の強みだと思います。
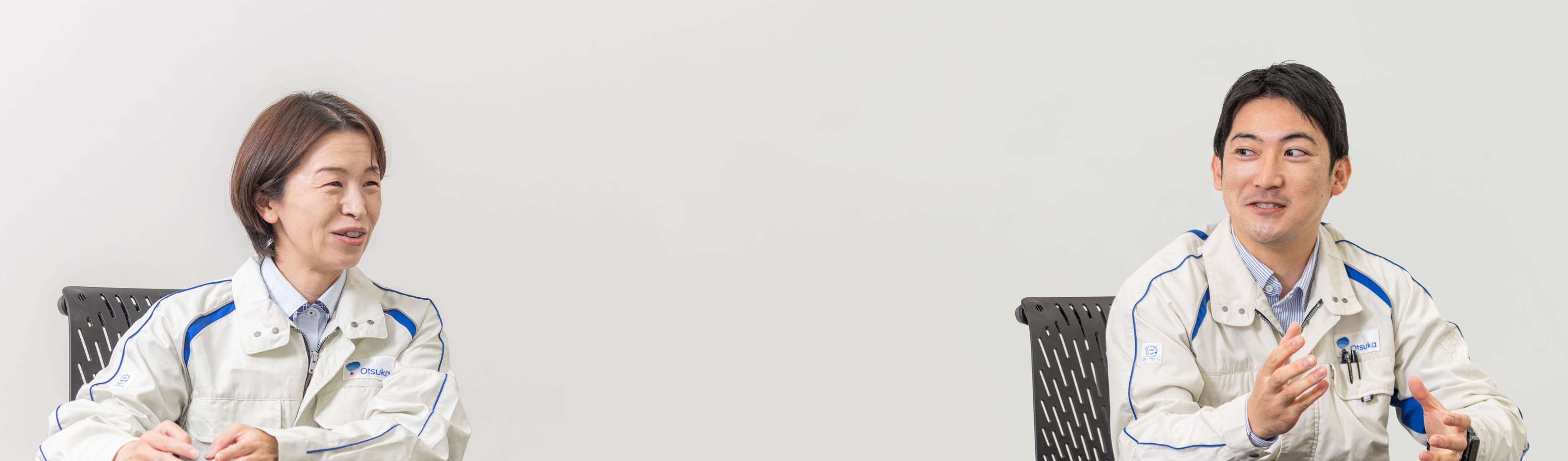
三本:当社は輸液の会社です。そのシェアは50%を越えていて、医療現場に行くと、大塚の輸液が使われていることが多いと思います。輸液は直接、患者さんの血管に入っていきます。だから安心して使える品質でなければなりません。品質は大塚製薬工場の命です。そのことに社員全員がこだわりを持っています。
椿山:製剤を入れている容器には、その会社の品質に対する考え方が反映されていると感じています。当社の製品は丈夫で持ちやすく、使いやすさにも配慮しています。自分の子供が入院した際にも、これなら安心だなと思いました。
韓 :容器本体やラベルにカラー印刷を施すと、視認性が高くなり、現場での取り違えの防止につながります。私たちの先輩が、そういう技術をはじめて中国に持っていったら、すごく評判が良かったそうです。結果的にビジネスとしても良い循環が生まれています。
藤原:私たちは今、環境にも配慮した容器の取り組みに力を入れています。そのひとつが、バッグ製品の薄肉化です。厚みが薄くても強度を保てるようなフィルムだったら、使用する樹脂材料の量を減らせて結果的に環境への負荷も抑えることが可能になります。そのために、材料メーカーだけに頼るのでなく、自分たちでも新しい樹脂の研究をしているのです。

藤原:釧路工場に勤務していた当時のことですが、すでにある生産ラインの中で、どうやって製剤や容器を作っていくか、これを考えるのがメインの仕事でした。製剤技術部が開発した製剤処方、生産技術部が開発した容器の製造方法、それらを実際の製造に落とし込むための条件出しです。
そのために日々、本社の各部署とのコミュニケーションを密接に取っていました。釧路にいても徳島が遠いと感じたことはないですね。
三本:輸液製剤の安定性を保つには、容器の作り方や、工場で安定的に製造を行う技術などが重要になります。そのためには、製剤技術部、生産技術部および工場の分室が一つのチームとなって開発に取り組む必要がありますから、そうしたコラボレーションが密に行える環境であることが大切なのです。
椿山:製品の開発期間は比較的短いですが、上市された製品は10年、20年、ときにはもっと長い年月にわたって使われ続けます。つまり、開発期間に比べて製品寿命のほうが圧倒的に長いのです。技術センターの役割は、製品を上市したら終わりではなく、その後もさまざまな課題に取り組み、上市後の問題をどれだけ抑えることができるかが重要になります。
ここでは、ひとつのフロアに各部署が集まっているので非常に風通しがよく、あらゆる対応の早さが強みです。
韓 :コミュニケーションやコラボレーションにおいて、風通しの良さは絶対に必要です。それは技術センターに限らないですね。当社では、チャレンジしたいことをすごく応援してくれます。私が他の新しい仕事も経験したいという要望を出したら、上司もそれを考慮して仕事をアレンジしてくれました。このような社風が次々と新製品・新技術の誕生につながっていると思います。